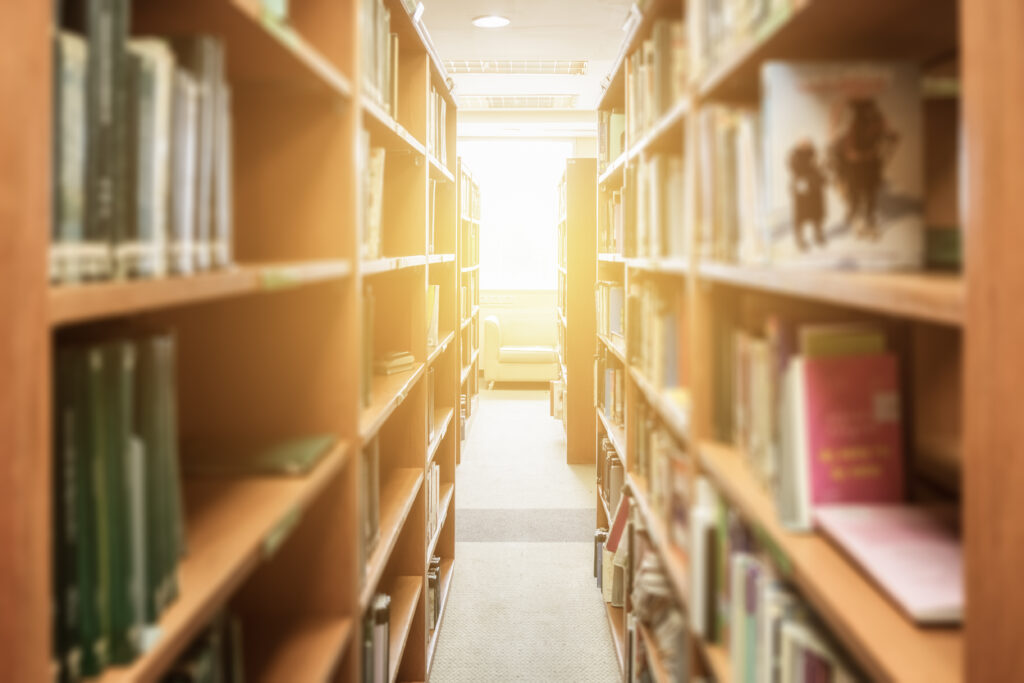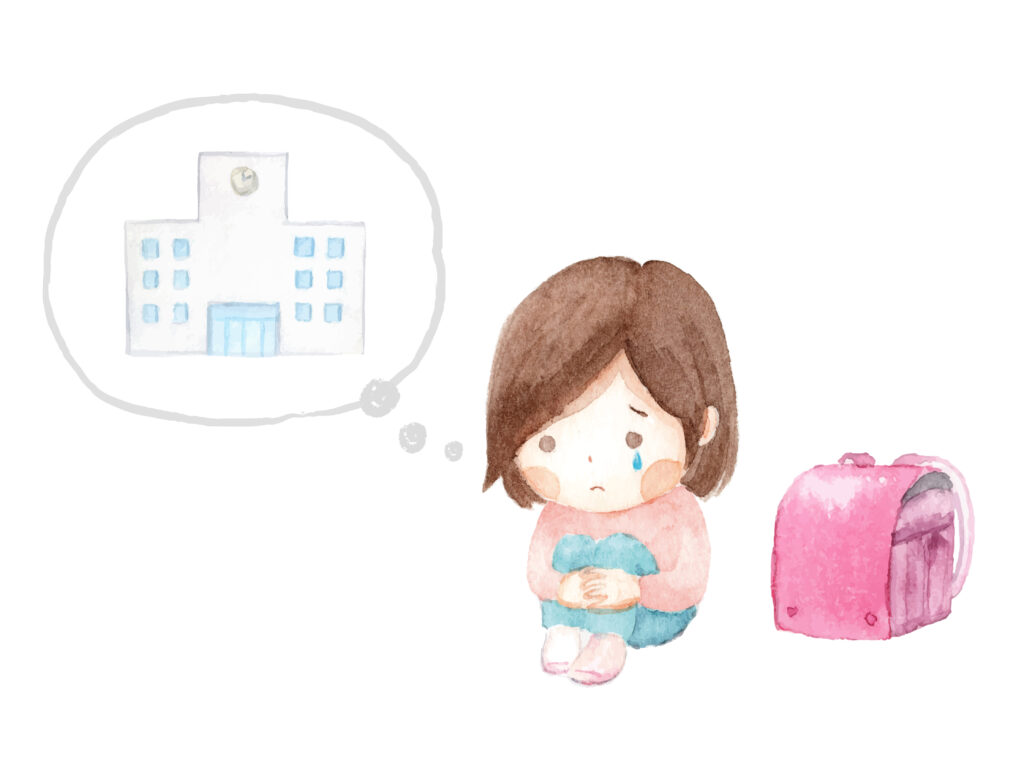everride– Author –
-

放課後等デイサービスにおけるICT活用:支援の質向上と業務効率化の可能性
近年、私たちの日常生活において、ICT(情報通信技術)は不可欠なツールとなっています。 この波は、障がい福祉分野、特に放課後等デイサービス(以下、放デイ)の現場にも押し寄せており、その活用によって、支援の質向上や業務効率化に大きな可能性が秘... -

【学校と放課後等デイサービス】役割の違いと連携による相互補完性
障がいのあるお子さんの保護者の方々から、「どちらも子どもを預かってくれる場所だけど、どう使い分けたらいいの?」といったご質問をいただくことは少なくありません。 また、それぞれの現場で働く支援者の方々にとっても、互いの役割を深く理解し、連携... -

発達障害と社会性:友達関係を育むための理解とサポート
【「友達って、どうやって作るんだろう?」「どうして、みんなみたいにうまく話せないんだろう?」】 「友達って、どうやって作るんだろう?」「どうして、みんなみたいにうまく話せないんだろう?」 発達障害のある方々の中には、このような悩みを抱え、... -

勉強の「やる気」を引き出すヒント~自分らしい学び方を見つける羅針盤~
「勉強のやる気が出ない…」「どうすれば集中できるんだろう?」誰もが一度は抱える悩みではないでしょうか。特に、障がいのある方々が自身の目標に向かって学習を進める際には、特有の困難に直面することもあります。 このテーマは、個人のモチベーション... -

発達障害のある中高生が学校行事を乗り越えるために
学校生活には、授業や日常の活動のほかに、運動会、文化祭、修学旅行などの「学校行事」が数多くあります。これらは子どもたちにとって学びと成長の場であり、多くの経験を積む貴重な機会でもあります。 しかし発達障害のある中高生にとっては、その非日常... -

場面緘黙(ばめんかんもく)のお子さんが困りやすい場面と支援のヒント
【 はじめに:場面緘黙とは?】 場面緘黙(選択性緘黙)は、特定の場面や人前で極度に緊張してしまい、話したくても話せなくなる状態を指します。家では普通に話せるのに、学校や公共の場ではまったく声が出なくなるなど、環境によって大きく差が出るのが... -

子ども時代に育む「共感力」:多様な社会を生き抜くための羅針盤
グローバル化と多様化が急速に進む現代社会において、私たちはさまざまな背景を持つ人々と共に生きていくことが求められています。 このような時代に、子どもの頃から育んでいきたい力の一つが、非認知能力の中でも特に注目される「共感力」です。 共感力... -

どこからが“障害者”? その境界線と、私たちが大切にすべき視点
「障がい者」と聞いて、あなたはどんな人を思い浮かべますか? 車いすを利用している方、白杖を持っている方、手話で会話をする方、あるいは発達障害や精神疾患のある方かもしれません。 しかし、実は「障がい者」の定義やその境界線はとてもあいまいです... -

【専門家が語る】児童福祉の現場で輝く!理学療法士の専門性と温かい支援
病院やクリニック、そして近年注目されている放課後等デイサービスなどの児童福祉施設にも、理学療法士(PT)が専門職として活躍しています。 「リハビリの先生」というイメージをお持ちの方も多いかもしれませんが、特に子どもたちの成長を支援する現場で... -

【専門家監修】不登校の背景にある発達障害:理解と適切な支援で、お子様の未来を拓く
「うちの子、最近学校に行きたがらない…」「もしかしたら、何か発達の問題があるのかも…」 不登校や登校しぶりのお子さんの中には、発達障害を持つお子さんや、その特性が部分的に見られるいわゆるグレーゾーンのお子さんが少なくありません。 不登校のき...