発達障害のある子どもには、環境や状況によって行動や能力の発揮度合いが大きく変わることがあります。この現象は決して「気分屋」や「わがまま」ではなく、その背景には発達特性や心理的な要因が深く関わっています。
1. 「家ではできる、外ではできない」場合
① 環境の変化による不安
発達障害のある子どもは、環境の変化に敏感です。家では家具の配置や音、におい、人の表情などが予測でき、安心して行動できます。しかし外では、環境が常に変化し、予測できない出来事も多いため、同じ行動が難しくなることがあります。
たとえば、家ではスムーズに歯磨きができるのに、外泊先や学校の宿泊学習では落ち着かなくてできない、といったケースです。
② 周囲からの視線や評価
外では「失敗したらどうしよう」「笑われたらどうしよう」という意識が強く働き、行動が抑制されることがあります。家ではリラックスできるため行動できても、外では緊張やプレッシャーで動けなくなるのです。これは特に不安の強いタイプのASDや場面緘黙の傾向がある子どもに多く見られます。
③ 感覚過敏の影響
外の環境は、音や光、人混みなどの刺激が多く、それらが集中や動作を妨げます。家では静かで落ち着いていても、外では感覚刺激によって注意がそがれ、行動ができなくなることがあります。
2. 「家ではできない、外ではできる」場合
① 場の空気や役割意識
学校や放デイなど外の場では、「みんなと一緒にやる」「これはやるべきこと」というルールが明確で、役割意識が働きやすくなります。そのため、家ではやらない宿題や手伝いも、外ではスムーズにこなせることがあります。
② モデルとなる存在
外では同年代や大人がやっている姿を目にしやすく、「やってみよう」という気持ちが生まれやすくなります。模倣は発達障害のある子どもにとって重要な学習方法で、家庭ではそのモデルが少ない場合、行動が引き出されにくくなります。
③ 外向きのエネルギー
外では“社会的な自分”を演じるためにエネルギーを集中的に使い、普段以上の力を発揮できることがあります。家ではそのエネルギーを充電するために動かず、できない姿が目立つというわけです。
3. 同じ行動でも「できる/できない」が変わる理由
このような現象は、能力そのものが変わっているわけではありません。大きく分けて次の要因が絡み合っています。
- 環境の構造化の度合い
外では時間割や指示が明確で、行動の順序がはっきりしていることが多い。家では曖昧なこともあり、次の行動が見えずに動けなくなることもある。 - 心理的負荷の違い
外では緊張が集中力を高める方向に働くこともあれば、逆に行動を妨げることもある。 - 感覚刺激の差
静かな家で集中できる子もいれば、逆に刺激がないと行動を始めにくい子もいる。 - モチベーションの源
外では人からの承認や評価がモチベーションになる子も多い。家ではそれが働きにくい。
4. 支援や工夫のポイント
「家ではできる、外ではできない」場合
- 外の環境でも家と同じ手順や道具を使えるようにする
- 事前に写真や動画で外の環境を見せ、予測可能性を高める
- 成功体験を小さく積み重ね、徐々に不安を減らす
「家ではできない、外ではできる」場合
- 外でできたことを家庭でも再現できるように、手順や支援方法を共有する
- 家庭でも“役割”や“見本”を設定する
- 家での行動に小さな報酬や達成感を組み込む
5. 保護者と支援者の連携
この現象を「なぜ家ではやらないの?」と叱責してしまうと、子どもは自己肯定感を失い、さらにできなくなることもあります。
保護者と支援者が情報を共有し、「環境や条件によって行動は変わる」という理解を持つことが重要です。外でできたことは、その成功の条件を家庭に持ち帰るヒントになります。
おわりに
発達障害のある子どもにとって、「できる」と「できない」は固定されたものではなく、環境・刺激・役割意識・心理的負荷といった複数の要因で大きく変わります。
家と外での差は、能力の有無を示すものではなく、その子が安心して力を発揮できる条件の違いを示すものです。
大人がすべきなのは、“どちらの姿もその子の本当の姿”として受け止め、必要な条件をそっと整えてあげること。それが、子どもたちの力をあらゆる場面で引き出すカギとなります。




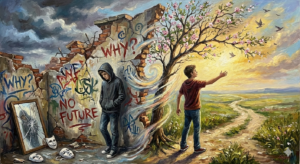





コメント