感情のコントロールが難しい子どもたち
発達障害の診断を受けたお子さまの中には、感情のコントロールが難しいケースが多く見られます。
例えば、友達や大人の何気ない一言をきっかけに感情が爆発し、相手をどなったり、ものを投げたりすることがあります。けれども時間が経つと、何事もなかったかのように落ち着きを取り戻すこともあります。
こうした「感情の起伏の激しさ」は、単なるわがままではなく、脳の働きや特性に深く関係しています。
発達障害の特性と感情の爆発
ADHD(注意欠如・多動症)の場合
ADHDの子どもに見られる特徴の一つに「衝動性」があります。
「思ったことをすぐに口にする」「やりたいことをすぐに実行してしまう」という行動は、周囲には「短気」「落ち着きがない」と見られることも少なくありません。
例:授業中に注意された瞬間に「なんでそんなこと言うの!」と怒鳴ってしまい、あとで「本当はそんなつもりじゃなかった」と後悔するケースもよくあります。
ASD(自閉スペクトラム症)の場合
ASDのお子さまは、こだわりが強かったり感覚が敏感だったりするため、思い通りにいかないときに感情が爆発することがあります。
「大切にしていたおもちゃを触られた」「音や光などの刺激が我慢できなかった」といった状況で、かんしゃくにつながるケースが多いです。
例:ある5歳の男の子は、給食の時間に苦手な匂いが漂うだけで机を叩いてしまい、泣きながら教室を飛び出してしまうことがありました。
「わがまま」ではなく「脳の特性」
発達障害のある方が感情をコントロールしにくい理由の一つに、ワーキングメモリの弱さが関係しています。
ワーキングメモリとは「その場で情報を一時的に保持しながら処理する力」で、これが少ないと「頭の中がいっぱい」になり、冷静な判断が難しくなります。
「どうしたらいいか分からない」「気持ちを言葉にできない」といった状況で、不安や苛立ちが爆発してしまうのです。
これは決して「わがまま」や「自分勝手」ではなく、脳の特性による困難さであることを、周囲が理解することが大切です。
感情コントロールの工夫と支援方法
怒りを感じたときに「6秒深呼吸する」「その場を離れる」など、自分なりのクールダウン方法を見つけることが効果的です。
「怒っていいんだよ。でも叩いたり壊したりしない方法で表そうね」と伝えることが、子どもの安心につながります。
運動は感情を安定させるホルモン(セロトニン、ドーパミン)の分泌を促します。
日常的に散歩やボール遊びを取り入れると、爆発の頻度が減りやすくなります。
例:小学生の男の子が、毎朝10分ランニングを取り入れるようになってから、授業中にイライラする回数が減ったという報告もあります。
「感情が爆発しやすい環境」を減らすことも重要です。
- ADHDの場合:タスクを一度に与えず、一つずつ伝える
- ASDの場合:マニュアルや視覚的なスケジュールを用意する
- 感覚過敏がある場合:イヤーマフやサングラスで刺激を減らす
こうした配慮により、不必要なストレスを減らすことができます。
家庭での工夫
- 感情が高ぶったときに逃げ込める「安心スペース」を作る
- 言葉にできないときに「気持ちカード」や「絵」を使って表現できるようにする
- 怒りが収まった後に「どうしたらよかったかな?」と一緒に振り返る
学校での対応
- 担任や支援員が「困ったときにできる合図」をあらかじめ共有する
- 教室で難しいときは、別室でクールダウンできる仕組みを用意する
- 「頑張れ」ではなく「一緒にやろう」と声をかけることで安心感を与える
年齢ごとの感情コントロール支援
幼児期は、感情を言葉で表現する力がまだ十分に育っていないため、「泣く」「叫ぶ」「物を投げる」といった行動で気持ちを表すことが多い時期です。
特に発達障害のあるお子さまは、「イヤ」「やめて」と伝える代わりに、強いかんしゃくとして表れてしまうことがあります。
支援の工夫
- 絵カードや表情イラストを使い、「悲しい」「楽しい」「怒っている」といった気持ちを視覚的に理解できるようにする。
- 感情が爆発する前に、親が「いまイライラしているかな?」と声をかけて気持ちを代弁する。
- 失敗しても「できなかったね。でも次にやってみようね」と肯定的な言葉で安心感を与える。
例:ブロック遊びでうまく積めずに泣き出したとき、「悔しい気持ちなんだね。じゃあ一緒にやってみようか」と声をかけると、落ち着きを取り戻しやすくなります。
小学生になると、言葉で気持ちを表現する力は育ってきますが、衝動性やこだわりから「怒りが先に出てしまう」ケースがよくあります。
友達関係や学習のプレッシャーが増えるため、感情爆発の場面が学校で目立ちやすくなる時期でもあります。
支援の工夫
- ソーシャルスキルトレーニング(SST)で「嫌なことを言われたら深呼吸してから答える」など、具体的な対処法を練習する。
- 「怒ってもいいけど、その場を離れようね」と代替行動を教える。
- 担任や支援員と連携し、困ったときにサインを出して別室に移動できる仕組みをつくる。
- 1日の予定を見通せるスケジュール表を活用して、不安を減らす。
例:授業中に指名されずに怒ってしまう子に対して、「次にあてるからね」と予告してあげると安心し、爆発を防ぎやすくなります。
思春期は、自己意識が強くなり、親や先生よりも「友達との関係」が感情を大きく揺さぶる時期です。
また、ホルモンバランスの影響で気持ちが不安定になりやすく、発達障害の特性と重なることで「周囲から理解されにくい怒り」や「孤立感」につながることもあります。
支援の工夫
- アンガーマネジメントの基本を教え、「怒りが出そうなときはスマホに気持ちを書き出す」など、自分に合った方法を一緒に探す。
- 信頼できる大人(先生・支援員・スクールカウンセラー)が相談役になる。
- 運動や趣味など「気持ちを吐き出す場」を生活に組み込む。
- 学校や家庭で「失敗しても大丈夫」という安心感を保証し、自尊心を守る。
例:中学生の女の子が、部活で意見が通らず泣き出してしまう場面がありました。担任が「意見をまとめてから伝える方法を一緒に考えよう」と提案し、紙に書き出す練習をすることで、落ち着いて自己主張できるようになりました。
児童発達支援の観点から
発達支援の現場では、感情のコントロールは「練習して育てる力」として位置づけられています。
- 成功体験を積ませる
「怒りそうになったけど深呼吸できたね」と小さな成功を褒めることで、自分で感情をコントロールできる自信につながります。 - ソーシャルスキルトレーニング(SST)
絵カードやロールプレイを通して「イライラしたときはこうする」と具体的な対処法を練習します。 - 感覚統合療法
ブランコやトランポリンなど体を使った遊びを通して、感覚刺激を調整し、情緒の安定を図ります。
発達支援の現場では、年齢や発達段階に応じたサポートを行うことが基本です。
- 幼児期:感情を「気持ちカード」などで見える化し、表現の方法を増やす
- 小学生:SSTで具体的な行動を学び、学校で使えるスキルを練習する
- 思春期:自己理解と自尊心のサポートを重視し、「自分らしく気持ちを表現できる」練習を行う
いずれの年齢でも、「感情を抑える」ことを目的とするのではなく、「感情を上手に扱えるようになる」ことを目標に支援していきます。
まとめ
感情のコントロールが難しいのは、発達障害の特性によるものであり、決して「甘え」や「わがまま」ではありません。
環境調整やアンガーマネジメント、運動習慣などを通して、少しずつ「自分で感情を扱える力」を育てていくことが大切です。
家庭、学校、専門機関が連携し、子どもが安心して気持ちを表現できる環境を整えることが、長期的な成長につながります。


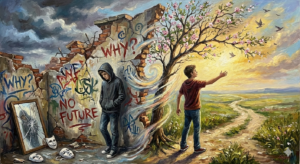







コメント