発達障害を持つお子様にとって、「断る」という行動は、自尊心や社会性を育む上で非常に重要なスキルです。しかし、「嫌なことをされても言葉にできない」「頼まれるとつい引き受けてしまい、疲弊してしまう」「断ったことで相手を不快にさせてしまうのではないか」といった悩みを抱えるお子様やご家族は少なくありません。
「断る」という行為は、相手の意図を理解する認知的な力、自分の気持ちを整理する感情のコントロール、そしてそれを適切に伝えるコミュニケーションスキルといった、複数の能力が複雑に絡み合って成立します。
発達特性を持つお子様にとって、これらのスキルを同時に習得することは容易ではありません。
本稿では、発達障害のあるお子様が「断る力」を段階的に身につけるための具体的な考え方、支援方法、そしてトレーニングの工夫について、児童福祉の専門家の視点から詳しく解説します。
なぜ「断る」ことが難しいのか?発達特性と関連する要因
発達障害のあるお子様が「断る」ことを苦手とする背景には、以下のような発達特性が深く関わっていると考えられます。
状況を理解し、適切に対応することの難しさ:
「今、この状況で断っても大丈夫なのか」「相手は本気で言っているのか、それとも冗談なのか」といった、その場の空気を読むことや、曖昧な状況を判断することが苦手なお子様もいます。
これにより、断るべき場面でためらってしまったり、逆に不適切なタイミングで断ってしまい、周囲との関係に摩擦が生じたりすることがあります。
相手の気持ちや意図を推測することの困難さ(自閉スペクトラム症(ASD)の特性):
ASDの特性を持つお子様は、他者の感情や思考を想像することが苦手な場合があります。
「断ったら相手はどう思うだろうか」「もし断らなかったら自分はどうなってしまうのか」といった、状況を多角的に捉えることが難しいため、結果として相手の要求をそのまま受け入れてしまうことがあります。
また、相手の表情や声のトーンから感情を読み取ることが苦手なため、断るタイミングや伝え方に迷いが生じることもあります。
自信のなさや自己肯定感の低さ:
過去の経験から「断ると嫌われるかもしれない」「怒られるかもしれない」といった不安が強く、自分の意見を言うことや要求を拒否することに強い抵抗を感じるお子様も少なくありません。
これは、発達障害の特性による困難さから、周囲の期待に応えられない経験を重ねてきた結果として生じることがあります。
感覚過敏やこだわりによる影響:
特定の感覚刺激を過度に避けたい、いつもと違うことへの強い抵抗があるといった特性が、「一緒に何かをする」という誘いを断る理由になることがあります。
しかし、その理由をうまく伝えられないために、周囲からはわがままと誤解される可能性もあります。
コミュニケーションスキルの未熟さ:
自分の気持ちを言葉で適切に表現することや、相手に配慮しながら断ることが難しい場合があります。
どのような言葉を選べば相手に理解してもらえるのか、どのように伝えれば角が立たないのかといった、高度なコミュニケーションスキルが求められるため、発達段階や特性によっては困難さを伴います。
「断る力」を育むための段階的なアプローチ
「断る」というスキルは、一朝一夕に身につくものではありません。
お子様のペースに合わせて、段階的に練習していくことが重要です。
まず、「嫌だ」「したくない」「疲れた」といったネガティブな感情を持つことは自然なことであり、それを表現しても良いという安心感を育てることが大切です。
【 具体的な取り組み例 】
絵カードや感情カードの活用: 笑顔、怒った顔、悲しい顔などの絵カードを使って、その時の自分の気持ちを指さしたり、言葉で言ったりする練習をします。「今、どんな気持ち?」と問いかけ、感情と言葉を結びつけるサポートをします。
気持ちを共有する時間: 日常会話の中で、「〇〇があった時、どんな気持ちになった?」と具体的に尋ね、お子様が自分の感情を振り返り、言葉で表現する機会を作ります。大人が自分の感情を話すことも、お子様の理解を助けます(例:「今日は疲れたから、少し休憩したいな」)。
感情日記: 絵や簡単な言葉で、その日に感じたことを記録する習慣を取り入れます。
ソーシャルストーリーの活用: 特定の状況でどのような気持ちになるか、それに対してどのような行動が考えられるかを、短い物語形式で提示し、感情の理解を促します。
ロールプレイなどを通して、具体的な断り方のフレーズや表現方法を練習します。
【 具体的な取り組み例 】
基本的な断りフレーズの練習: 「今はできません」「ちょっと難しいです」「今日はやめておきます」「ありがとう、でも大丈夫です」など、シンプルで使いやすいフレーズを繰り返し練習します。
表情や声のトーンの練習: 断る時の適切な表情(困った顔、申し訳なさそうな顔など)や声のトーン(落ち着いた声、はっきりとした声など)も一緒に練習します。鏡を見ながら練習するのも有効です。
代替案を提示する練習: 可能な範囲で、「〇〇ならできるよ」「明日はどうかな?」など、代替案を示すことで、相手に配慮する気持ちを伝える練習をします。
断る理由を簡単に伝える練習: 「疲れているから」「宿題があるから」など、簡単な理由を添えて断る練習をします。ただし、理由を詳細に説明することが苦手な場合は、無理に伝える必要はありません。
「NO」カードやジェスチャーの活用: 言葉で伝えることが難しい場合は、「NO」と書かれたカードを見せたり、手を横に振るジェスチャーを使ったりする方法も有効です。
ロールプレイ: 親御さんや支援者が相手役になり、様々な状況を想定して断る練習を行います。最初は成功しやすい簡単な場面から始め、徐々に難易度を上げていきます。
小さなことからで良いので、実際に断る経験を積み重ね、成功体験を増やしていくことが重要です。
【 具体的な取り組み例 】
家庭内での練習: 親御さんがお子様に何かを頼んだ際に、お子様が「今はできない」と断ったら、それを尊重し、「ちゃんと自分の気持ちを言えたね」と褒めます。
遊びの中での練習: 友達との遊びの中で、気が進まない誘いがあった際に、練習した断り方を試せるように促し、後で「上手に断れたね」と認めます。
視覚的なサポート: 断ることができた回数を記録するシートを作り、目標を達成したら一緒に喜ぶなど、成功体験を可視化します。
「断ることは悪いことではない」という認識を共有: 絵本やソーシャルストーリーなどを活用し、断ることは自分を守る大切な権利であり、相手との健全な関係を築く上で必要なスキルであることを伝えます。
具体的な支援アイデア
コミュニケーションカードの活用:
言葉でのコミュニケーションが難しいお子様には、「NO」「パス」「ちょっと待って」などの文字やイラストが描かれたカードを用意し、状況に応じて提示できるようにします。
ソーシャルストーリーの作成:
お子様が直面しやすい具体的な場面(例:「友達がおもちゃを貸してと言ってきた時」「遊びに誘われた時」)を想定したソーシャルストーリーを作成し、断るという選択肢とその結果を視覚的に理解できるようにします。
タイマーやアラームの活用:
「〇〇が終わったら休憩したい」という気持ちを伝えるのが難しい場合、タイマーをセットして「タイマーが鳴ったら休憩する」というルールを事前に決めておくことで、直接的な拒否を避けながら自分の要求を通しやすくします。
アンガーマネジメントとの連携:
断ることで相手が怒るのではないかと不安を感じるお子様には、相手の怒りの感情に対処する方法や、自分の気持ちを落ち着かせるためのアンガーマネジメントの手法を教えることも有効です。
ペアレントトレーニングやSST(ソーシャルスキルトレーニング)の活用:
専門家の指導のもと、親御さん自身が効果的な支援方法を学んだり、お子様が他者との関わり方を練習したりする機会を持つことも重要です。
周囲の理解と環境調整の重要性
お子様が「断る力」を身につけるためには、周囲の大人の理解と協力が不可欠です。
お子様の気持ちを尊重する姿勢: お子様が「嫌だ」と言った時には、頭ごなしに否定するのではなく、まずはその気持ちを受け止め、「そうなんだね」と共感することが大切です。
「断っても大丈夫」という安心感のある環境づくり: 家庭や学校などの環境において、お子様が安心して自分の意思を表明できる雰囲気を作ることが重要です。
他のお子様への配慮: 他のお子様にも、「断ることは悪いことではない」「相手の気持ちを尊重すること」を教え、発達障害のあるお子様の特性について理解を促すことも大切です。
学校や支援機関との連携: お子様の特性や練習の進捗状況について、学校や放課後等デイサービスなどの関係機関と情報を共有し、連携を取りながら支援を進めていくことが望ましいです。
まとめ
発達障害のあるお子様が「断る力」を身につけることは、自己肯定感を高め、より良い人間関係を築くための大切な一歩です。
焦らず、段階的に、そして何よりもお子様の気持ちに寄り添いながら、成功体験を積み重ねていくことが重要です。
周囲の大人が温かく見守り、適切なサポートを提供することで、お子様は自信を持って自分の意思を表現できるようになり、より主体的な生活を送ることができるようになるでしょう。

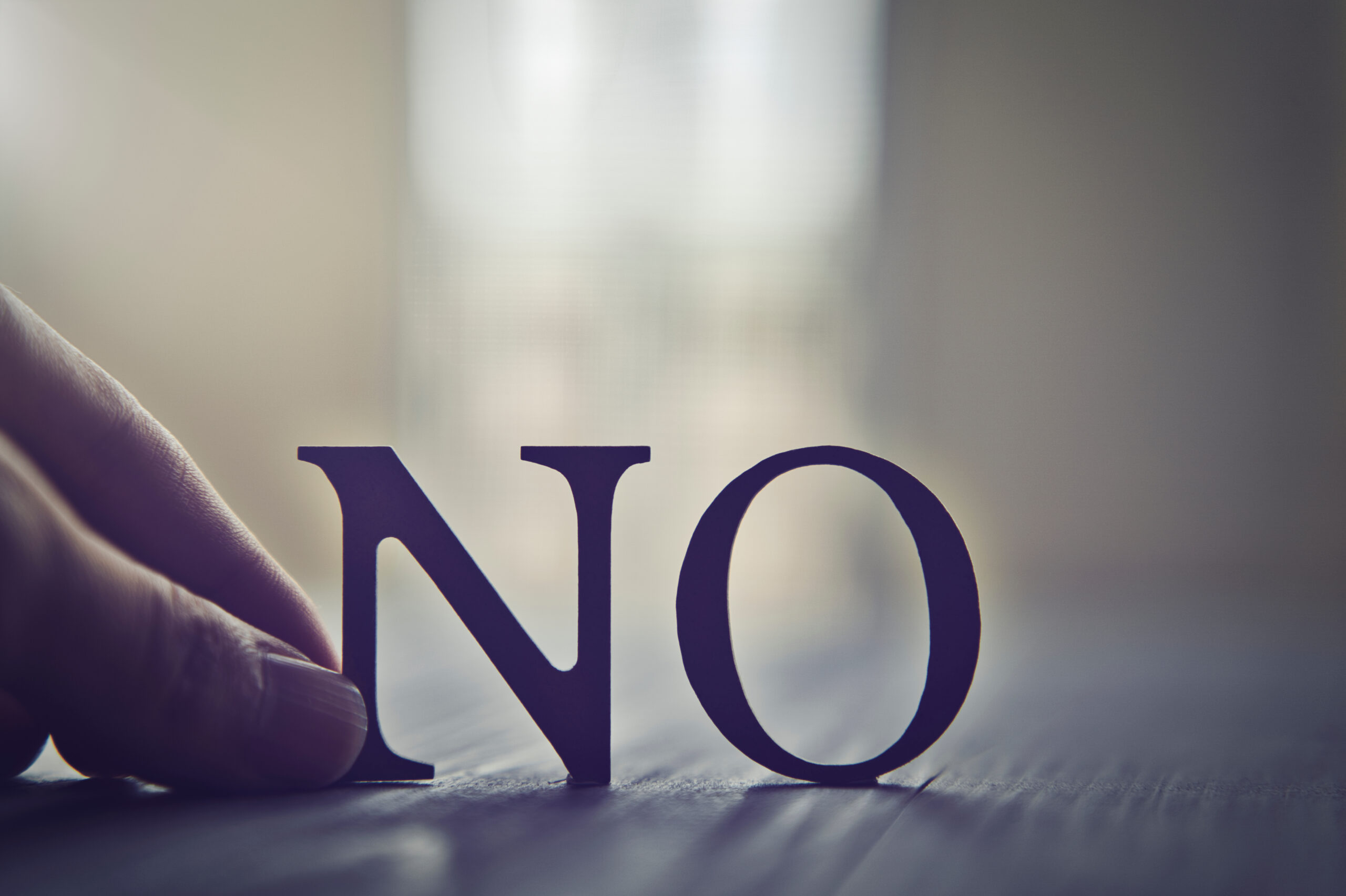








コメント