はじめに
新年度を迎える春は、進級や進学にともない、子どもたちの生活環境が大きく変わる時期です。クラスの顔ぶれが変わったり、教室の場所が変わったり、初めての教科や先生に出会うこともあるでしょう。こうした変化に対応するのは、大人にとっても簡単なことではありません。
特に発達障害のあるお子様にとっては、「いつもと違う」状況が強いストレスとなり、不安や混乱が表出しやすくなります。その影響から、教室内が落ち着かない雰囲気になってしまうこともあるかもしれません。
よくある指示の一つに「静かにしなさい」という言葉がありますが、このような言葉がそのまま通じず、行動に結びつかないケースは少なくありません。では、どうすれば子どもたちに「静かにする」という行動を理解してもらえるのでしょうか?
今回は、発達障害の特性に応じた具体的な対応の工夫について、一例をご紹介します。
特性によって対応が違う
「静かにしなさい」といった一言の指示がうまく伝わらないのは、決して子どもが悪いわけではありません。背景には、発達障害のあるお子様たちがもつ特性が関係しています。
そのため、言葉かけや対応の仕方は、それぞれの子どもの特性に合わせて工夫する必要があります。
「何度言っても伝わらない」と感じたときこそ、私たち大人のほうが「伝え方」を見直すチャンスかもしれません。特性に応じた理解と支援が、お子様との信頼関係の土台となっていくのです。
その1 ~ ASD(自閉スペクトラム症)の場合
ASDのお子様は、以下のような特徴をもつことがあります。
・相手の気持ちを読み取ることや、空気を読むことが難しい
・言葉を文字通りに受け取るため、冗談や皮肉が通じにくい
・興味やこだわりが強く、予定が急に変わると混乱しやすい
・聴覚や触覚などに過敏さをもっていることがある
中でも、「アスペルガー症候群」と呼ばれるタイプのお子様は、言葉の発達に遅れがない一方で、
・思ったことをすぐ口に出してしまう
・一方的に話し続けてしまう
といった特徴があり、コミュニケーションにすれ違いが生まれることもあります。
そのため、教室内で静かにしなければならない場面でも、自分の気になったことを突然話し出してしまうことがあります。
では、「静かにする」という行動を、ASDの特性を持つお子様にどのように伝えればよいのでしょうか?
1.「静かな状態」を体感させる
まず大前提として、「静かにする」という言葉自体が、抽象的でわかりにくいという点があります。
特性のあるなしに関わらず、子どもたちは「静か」とはどのような状態かを実際に経験しないと、頭で理解するのは難しいものです。
たとえば、教室で全員に一度手を止めてもらい、「今のように音がしない状態が“静か”なんだよ」と伝えることで、身体感覚と結びついた理解を促すことができます。
さらに、「今、〇〇さんは静かにできているね」と具体的に誰かの行動をフィードバックとして伝えると、モデルができてより伝わりやすくなります。
2.「静かな状態」を映像で見せる
想像する力や抽象的な表現を理解することが難しいお子様には、「見てわかる」情報を活用するのも効果的です。
たとえば、過去に自分が静かに過ごせていた時の様子を録画して見せたり、モデルとなる他の子の映像を見せたりする方法があります。
「このときの〇〇くん、静かに机に向かっていたね」「お話をせずに先生の話を聞けていたね」と、具体的な行動に注目してフィードバックを行うと、視覚からの理解が深まります。
その2 ~ ADHD(注意欠如・多動症)の場合
ADHDのお子様は、主に以下のような特性がみられます。
・注意力が散漫で、一つのことに集中し続けるのが難しい
・落ち着きがなく、じっと座っていられない
・衝動的に行動してしまい、後先を考える前に動いてしまう
このような特性から、「静かにしなさい」と言葉で伝えても、その言葉自体が耳に入らなかったり、意味がすぐに飛んでしまうことがあります。
では、どのような工夫が効果的でしょうか?
1.視覚から伝える
ADHDのお子様は、聴覚よりも視覚の情報のほうが入りやすい場合があります。
そのため、「静かにしようね」と口頭で伝えるだけでなく、イラストカードや視覚支援グッズを活用するとより効果的です。
たとえば、「お口チャック」のイラストや、「耳をすませて聞く人」のマークなどを提示することで、視覚的に状況を理解しやすくなります。
また、短く・具体的に伝えることも大切です。「静かにして」よりも「お口を閉じよう」「声は出さないよ」など、行動レベルで示す言葉にしましょう。
2.発散させる・区切りをつける
ADHDの多動性や衝動性の背景には、脳内の神経伝達物質「ドーパミン」の働きが関係しているともいわれています。
ドーパミンが過剰に分泌されている状態では、興奮状態が続き、じっとすることが難しくなります。
そんなときは、「静かにさせる」前に、一度体を動かす時間を取り入れて「発散」することが有効です。
たとえば、授業の前に軽いストレッチを入れたり、席を立って体をほぐすアクティビティを取り入れたりすると、落ち着きを取り戻しやすくなります。
静かにすることだけを目的にするのではなく、「落ち着くための準備」として体を動かす時間を位置づけることで、お子様自身も無理なく環境に順応しやすくなります。
まとめ
新年度は、大人にとっても子どもにとっても、大きな変化に適応するための「助走期間」です。
この時期にこそ、それぞれの子どもがもつ特性を理解し、一人ひとりに合った関わり方を意識することが、スムーズな学校生活の土台を築くことにつながります。
発達障害のあるお子様たちが、「できない」「落ち着かない」と評価されてしまう前に、まずは私たち大人が「伝え方」や「関わり方」を見直してみませんか?
特性を正しく理解し、あたたかく、具体的に支援することが、子どもたちの安心と成長につながっていくのです。


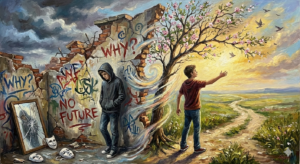







コメント