私たちは日常生活の中で「見える」「聞こえる」「触れる」「におう」「味わう」といった感覚を自然に使っています。けれど、人によってその感じ方には大きな幅があります。たとえば「まぶしい」と思う光でも、ある人にとっては耐えられないほど強烈だったり、逆に「暗い」と感じてしまったりすることもあります。こうした感覚の違いは、暮らしやすさを考えるうえで欠かせない視点です。
◆感覚の幅の広さ
感覚には「敏感すぎる」場合と「感じにくい」場合があります。
音に敏感な人は、駅や商業施設の雑音が頭に響き、会話に集中できなくなることもあります。
一方で音を感じにくい人は、近くで車が迫っていても気づかず危険につながることがあります。
同じように、触感に敏感な人は衣服のタグや素材が痛みに近い刺激に感じられることもあります。逆に感覚が鈍い人は暑さ寒さを感じにくく、体調を崩すまで気づかないこともあります。
このような感覚の差は、発達障害や感覚過敏・鈍麻といった特性を持つ人に限らず、誰にでも少なからず存在するものです。疲れているときに音が気になる、風邪をひいたときににおいに敏感になるなど、日常的にも私たちは感覚の揺らぎを経験しています。
◆暮らしやすさを左右する要因
感覚の違いは「どこで暮らすか」「どんな環境で過ごすか」に直結します。
例えば、オフィスで照明が強すぎると、ある人は頭痛を訴え、別の人は集中力を失います。反対に、少し暗めの照明の方が落ち着ける人もいます。住宅でも同じで、窓からの光や外の音の入り方一つで、暮らしやすさの感じ方は変わります。
公共交通機関や商業施設では、BGMやアナウンスの大きさが利用者に影響します。最近は「音の少ない時間」を設定する店舗や、照明を落として営業する「やさしい時間」を設けるショッピングセンターも出てきました。これはまさに、感覚の違いを尊重した取り組みといえます。
◆暮らしやすさを広げる工夫
感覚の違いを考えるとき、大切なのは「正解を一つに決めないこと」です。ある人にとって快適な環境が、別の人にとっては負担になり得るからです。だからこそ、工夫の幅を持たせることが求められます。
・照明の強さを調整できるスイッチ
・音量を選べるアナウンスや案内
・衣服の素材やタグの有無に配慮した商品
・においを抑えた公共空間のデザイン
こうした選択肢があるだけで、多くの人が自分に合った暮らし方を選びやすくなります。
◆感覚の違いは個性
感覚の差は、ときに不便さを生む一方で、強みになることもあります。
・においに敏感な人は、食材の鮮度や異変を早く察知できる
・色の違いに敏感な人は、デザインや品質管理に優れる
・細かな音の違いを聞き取れる人は、音楽や機械の調整に長けている
つまり感覚の違いは「困りごと」であると同時に「能力」でもあるのです。その多様さを理解し活かすことは、社会全体の豊かさにつながります。
◆まとめ
感覚の違いは目に見えにくいものですが、誰にでも存在します。その差を意識しないまま「これが普通」と決めてしまうと、一部の人にとって暮らしにくい環境が生まれてしまいます。逆に、違いを前提にした工夫を取り入れれば、誰もが自分らしく安心して暮らせる社会に近づきます。
暮らしやすさを考えるとき、「自分にとって快適」だけでなく「他の人にとってどうだろう」と想像してみる。そこから多様な感覚を尊重した社会づくりが始まります。
感覚の違いは、単に「配慮すべき特性」という枠を超えて、私たちの暮らし全体を見直すきっかけにもなります。例えば、静かな環境を好む人がいる一方で、少し音楽が流れている方が安心できる人もいます。この違いを「お互いに不便をかけるもの」と捉えるのではなく、「どうすれば共に過ごしやすい場になるか」を考える視点に立つと、社会のデザインそのものがより柔軟で多様なものになります。
また、感覚に配慮した工夫は、結果的に多くの人にとって快適さを生み出します。駅や商業施設での案内表示が文字だけでなく色やアイコンで示されていることは、視覚や読み取りの特性に関係なく誰にとってもわかりやすい工夫ですし、照明を少し落としたカフェの空間は、過敏さに配慮しながら「落ち着ける雰囲気」として一般にも喜ばれています。
つまり「感覚の違いから暮らしやすさを考えること」は、特定の人への支援にとどまらず、社会全体の質を底上げすることにつながります。多様な感覚の世界を互いに尊重し合うことで、「みんなにとって心地よい社会」に近づいていけるのです。


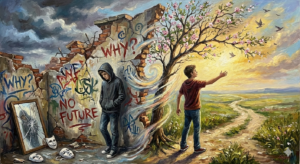







コメント