障がいのあるお子さまや、発達に特性のあるお子さまが、自分らしく成長し、安心して生活していけるように、年齢や成長段階に応じたさまざまな支援制度・福祉サービスが用意されています。
お子さま一人ひとりに合った支援を早めに知り、適切につなげていくことで、ご本人だけでなくご家族の生活や心のゆとりにもつながっていきます。
ここでは、乳幼児期から成人期まで、それぞれの時期に利用できる主な福祉サービスをご紹介いたします。
【1】乳幼児期(0~6歳)
〜「気づき」と「早めのサポート」が大切な時期〜
この時期は、成長の個人差が大きく、「少し気になる」「他の子と違うような気がする」といった悩みを抱える保護者の方も多くいらっしゃいます。
・乳幼児健診・発達相談
各市区町村で実施される健診などで発達の遅れに気づいた場合、保健センターや発達支援センターなどで相談が可能です。気になることがあれば、早めの相談が安心につながります。
・児童発達支援(通所支援)
お子さんが施設に通いながら、ことば、運動、社会性などの発達を促す療育を受けられるサービスです。遊びや日常の活動を通じて、楽しみながら必要な力を育てていきます。
・保育所等訪問支援
保育園や幼稚園などに通っているお子さんが、集団の中で過ごしやすくなるよう、専門スタッフが訪問して、先生方への助言や環境調整を行います。
【2】学齢期(小・中・高校生)
〜学びながら「できること」を広げていく時期〜
学校生活が始まり、集団の中で生活する機会が増える時期です。それぞれのお子さんの特性に合った教育と支援を受けることが大切です。
・特別支援学級・特別支援学校
通常の学級では対応が難しい場合、特別支援学級や特別支援学校で、一人ひとりの特性に応じた教育を受けられます。個別の学習指導や生活面の支援が行われます。
・放課後等デイサービス
学校の終わったあとや長期休暇中に利用できる施設で、生活スキルの習得、学習支援、集団活動などを行います。ご家庭と学校以外に安心して過ごせる「第3の居場所」としても大切な役割を果たします。
・相談支援(障害児相談支援)
今後どのようなサービスが必要か、どんな支援があるのかを一緒に考えてくれる相談員(相談支援専門員)がおり、利用までの手続きをサポートしてくれます。
【3】高校卒業後・若者の時期
〜社会参加や自立に向けた準備を進める時期〜
学校を卒業した後は、働く・暮らす・社会と関わるといった「自立」に向けたステップが始まります。
・自立訓練(生活訓練)
自分で食事を作る、掃除をする、お金を管理するなど、日常生活のスキルを身につける練習ができるサービスです。将来的に一人暮らしや就労を目指す方に適しています。
・就労移行支援
一般企業で働くことを目指す人のために、職場体験やビジネスマナー、履歴書の書き方など、就職活動に必要な支援を行います。就職後も職場定着支援を受けることができます。
・計画相談支援
福祉サービスを利用する際に必要な「サービス等利用計画」の作成を通じて、将来の生活を見据えた支援計画を立てます。
【4】成人期(18歳〜)
〜地域の中で自分らしく暮らすためのサポート〜
大人になった後も、それぞれのライフスタイルに応じた支援を受けることができます。
・ 就労継続支援(A型・B型)
一般企業での就労が難しい方に対して、支援を受けながら働くことができる福祉的就労です。
・A型:雇用契約があり、お給料が支払われます。
・B型:体調や能力に合わせた作業で、工賃が支払われます。
・グループホーム
支援スタッフがいる共同生活の場で、日常生活の支援を受けながら地域の中で自立した生活を送ることができます。
・生活介護
日中、施設で活動しながら、入浴や食事、創作活動やリハビリなどの支援を受けられます。
最後に
障がいのあるお子さまが、その子らしく安心して成長していくためには、「早めの気づき」と「地域とのつながり」がとても大切です。
「まだ小さいから大丈夫」「こんなことで相談してもいいのかな?」と思うような小さな不安や疑問でも、どうぞ気軽にご相談ください。
学校、地域の相談支援専門員、医療・福祉の機関が連携して、お子さまとご家族の歩みを支えていきます。
一人で悩まず、一緒に考えていきましょう。


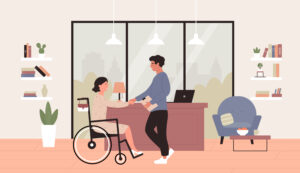







コメント