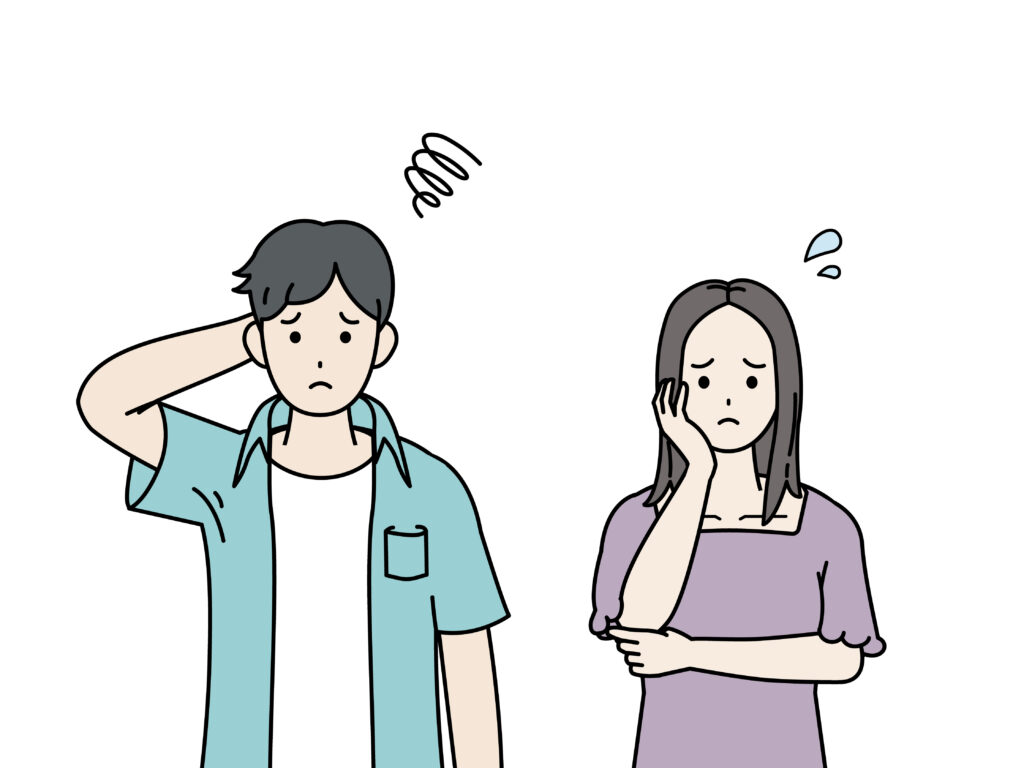支援の実践方法・関わり方– category –
-

放課後等デイサービスにおけるデジタルデトックスの善悪
放課後等デイサービスにおけるデジタルデトックスの善悪 ―「取り上げる支援」から「使いこなす支援」へ― 近年、放課後等デイサービスの現場でも「デジタルデトックス」という言葉を耳にする機会が増えてきた。スマートフォン、タブレット、ゲーム機などの... -

感情のコントロール支援〜怒りや不安への具体的な対応(タイムアウト・視覚支援など)〜
「怒ったら止まらない」「不安になるとパニックになってしまう」 発達特性のあるお子さんと関わる中で、こうした場面は決して珍しくありません。感情のコントロールは、大人でも難しいこと。ましてや、発達段階にある子どもにとってはなおさらです。 ただ... -

児童発達支援とハロウィン〜“行事”を通して育つ子どもの力〜
【「ハロウィンって、ただの仮装イベントじゃないの?」】 10月になると、街中や保育・療育の現場でもハロウィンの飾りや仮装をよく目にします。 児童発達支援の現場でも、ハロウィンは子どもたちが楽しみにしている行事のひとつです。 でも、実はこの「ハ... -

小学生期から育てたい「生活スキル」〜将来の自立につながる小さな一歩〜
【1. なぜ小学生期からの生活スキルが大切なのか】 小学生の時期は、「自分でできること」を少しずつ増やしていく大事なステップです。特に発達障害を持つお子さんにとっては、社会生活や将来の自立に直結するスキルを早い段階から繰り返し練習することが... -

日常生活の中で「できた!」を感じる瞬間 〜放課後等デイサービスから見える子どもの成長〜
【◆はじめに】 放課後等デイサービスで子どもたちと過ごしていると、日常の中で「できた!」という小さな成功体験に出会うことがあります。それは、大人から見れば些細なことかもしれません。しかし子どもにとっては大きな一歩であり、自己肯定感を育み、... -

ネグレクトとは何か 〜子どもを守るために私たちができること〜
【】 「ネグレクト」という言葉は、日本語では「育児放棄」と訳されることが多く、保護者が子どもに対して必要な養育やケアを怠る行為を指します。具体的には、以下のような行動が含まれます。 • 子どもに十分な食事を与えない• 適切な衣服や住居を提供し... -

日常生活の困り感と支援方法~こんなときどうする?日常の困り感をサポートするヒント集
発達障害を持つ人々は、日常生活において様々な弊害に直面することがあります。 これには、時間管理の困難、整理整頓の苦手さ、対人関係のトラブル、感覚過敏、社会的な期待への対処、就労支援の不足などが含まれます。 【発達障害による日常生活の弊害】 ... -

発達障害のある子どもの「できる」と「できない」が場所によって変わる理由
発達障害のある子どもには、環境や状況によって行動や能力の発揮度合いが大きく変わることがあります。この現象は決して「気分屋」や「わがまま」ではなく、その背景には発達特性や心理的な要因が深く関わっています。 【】 ① 環境の変化による不安 発達障... -

遊びは最高の学び ― 成長を支える遊びの工夫
【こどもとの遊び方とは?】 こどもとの遊びは、ただ楽しく時間を過ごすためだけではありません。こどもとの遊びは、親子の時間を豊かにするだけでなく、心と体、ことばや社会性など、成長に欠かせない要素を育てる大切な活動です。 遊びは「楽しい」から... -

聴覚過敏の子どもに寄り添う ― イヤーマフが広げる安心の可能性
【】 イヤーマフは、耳を覆って周囲の音をやわらげたり遮ったりする防音グッズです。工事現場や空港、射撃場など、騒音の多い場所で働く人の耳を守るために使われてきました。最近では、音に敏感な子どもや大人が日常生活の中で安心して過ごすためのアイテ...