「障害者雇用」という言葉は耳にする機会が増えてきましたが、
「実際にはどんな仕事をしているのか?」「職場ではどんな配慮がされているのか?」まで知っている人は、まだ少ないかもしれません。
「特別な仕事をしているんでしょ?」「サポートが大変そう」など、誤解を含んだイメージを持たれることもあります。
でも、実際の障害者雇用は、もっとずっと多様で柔軟です。
働き方も支援のかたちも、「その人らしさ」に寄り添いながら広がっています。
この記事では、障害者雇用の基本的な仕組みから、具体的な仕事内容、そして職場で行われている工夫や変化について、
福祉の現場の視点も交えて、やさしく解説します。
★障害者雇用ってなに?
日本には「障害者雇用促進法」という法律があります。
この法律では、一定の規模以上の企業に対し、従業員のうち一定割合を「障害のある人」とする義務(法定雇用率)を定めています。
2024年時点の民間企業の法定雇用率は 2.5%。
つまり、従業員が40人以上いる企業では、少なくとも1人は障害者を雇う必要がある、ということになります。
さらに2026年には 2.7% へと引き上げられる予定で、企業の障害者雇用は「特別な配慮」ではなく「社会の当たり前」として定着しつつあります。
★実際には、どんな仕事をしているの?
「障害がある方が働く」と聞くと、どこか限定的な仕事を想像してしまうかもしれません。
でも実際には、障害の種類や特性、その人の得意・不得意に応じて、とても幅広い職種・働き方が実現されています。
◯ 発達障害・精神障害のある方の例
- データ入力、書類整理、スキャニングなどの事務補助
- 備品管理や郵便物の仕分け、社内配達
- 集中力を活かしたWeb制作、プログラミングなどの専門業務
◯ 知的障害のある方の例
- オフィスや店舗での清掃やゴミ回収
- 飲食店での厨房補助、テーブル拭き、配膳サポート
- 工場での検品・仕分け・ラベル貼り
◯ 身体障害のある方の例
- パソコンを用いた事務職
- 電話応対や受付業務(聴覚障害がある場合はチャットや筆談)
- CADオペレーターやデザイン系などの専門職
★職場での「配慮」って、どんなことをしているの?
障害者雇用においては、「合理的配慮」という考え方が重要です。
これは、障害のある人が他の人と同じように働けるように、必要な工夫をすることを意味します。
たとえば……
- 指示を口頭だけでなく紙やチャットで丁寧に伝える
- 作業手順を写真やイラストでわかりやすく提示する
- 感覚過敏がある方には、静かな場所での作業環境を整える
- 通院や体調に応じて、勤務時間を柔軟に設定する
- 手すり・スロープ・筆談ツールなどの物理的な配慮
これらは「特別扱い」ではなく、
その人が「本来の力を発揮できる環境をつくる」という視点に立った配慮です。
★障害者雇用がもたらす、職場全体へのよい変化
実際に障害者雇用を取り入れている企業からは、次のような前向きな声が多く聞かれます。
「職場の雰囲気が柔らかくなった」
「業務の見直しが進み、職場全体が効率的になった」
「指示の出し方や接し方を見直す中で、コミュニケーションが円滑になった」
「”誰かの力になる経験”が、社員の成長にもつながった」
障害のある方への配慮を進めることが、実はすべての人にとって働きやすい職場づくりにつながっているのです。
★児童福祉の視点から伝えたいこと
私たち福祉に関わる者として、子どもたちにこう伝えたいのです。
「将来、どんなかたちであっても、自分の力を社会の中で発揮できるよ」と。
今、発達障害や知的障害、身体障害のある子どもたちが、学校や福祉施設で自分らしさを大切にされながら育っているように、
大人になってからも「その人らしく働く」場があることは、とても大切なメッセージです。
保護者の方も、「うちの子に将来仕事ができるの?」という不安を抱えることがあると思います。
でも、障害者雇用の現場では、多くの人が、自分の強みを活かして働いています。
★まとめ:障害者雇用は、「ちがいを活かす」社会への一歩
障害者雇用というと、少し構えてしまう人もいるかもしれません。
でも、実際には「その人に合った仕事を、無理なくできる形で任せる」という、誰にとっても当たり前の働き方の一つです。
「障害があるからできない」のではなく、
「どうすれば、その人が力を発揮できるか」を考えること。
それは、これからの共生社会に必要な視点であり、
私たち一人ひとりが「ちがいを受け入れる」から「ちがいを活かす」へと変わっていくための第一歩です。
障害者雇用はきっと、『特別なこと』ではなく、『当たり前の選択肢』になっていくはずです。
障害者雇用が、社会にとってもっと身近な存在になることを願っています。


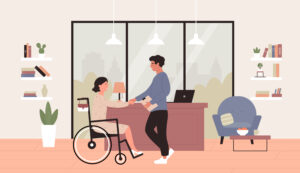







コメント